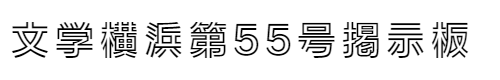掲示板
BBS管
管理者さん (8ywajz8f)2023/12/18 14:17 (No.1012800)削除①『本郷館』 藤野燦太郎著
本作品に対する、感想、ご意見をお待ちしております。
「返信欄」から投稿願います。
本作品に対する、感想、ご意見をお待ちしております。
「返信欄」から投稿願います。
匿名さん (90kuq21b)2024/1/29 23:26削除
「本郷館」について 藤野
〈創作意図、狙い〉
シェークスピアから芥川、太宰、村上など過去の作品をすべて知っているchat gptが思いつかない物語を作ってみようと思いました。
〈完成度〉
某氏の「小説作法」にはこうあります。
「小説は、まず読者をこっちに向かせることから始めなければならない」
恋愛小説に飢えている女性を振り向かせることが出来たか?
「主観的に貴重なものが、そのまま客観的に貴重とは限らない」
「作者と読者の間には深くて暗い河がある」
さて2年後にあの男はこんな話を書いていたと思い出してもらえるだろうか?
〈創作意図、狙い〉
シェークスピアから芥川、太宰、村上など過去の作品をすべて知っているchat gptが思いつかない物語を作ってみようと思いました。
〈完成度〉
某氏の「小説作法」にはこうあります。
「小説は、まず読者をこっちに向かせることから始めなければならない」
恋愛小説に飢えている女性を振り向かせることが出来たか?
「主観的に貴重なものが、そのまま客観的に貴重とは限らない」
「作者と読者の間には深くて暗い河がある」
さて2年後にあの男はこんな話を書いていたと思い出してもらえるだろうか?
藤
藤堂勝汰さん (8ywajz8f)2024/2/9 15:37削除本郷館(藤野燦太郎さん)を読んで
数年前に藤野さん企画の林芙美子の足跡を辿る文学散歩に参加させてもらった事がある。同じ時期に放浪記を読んだ。
今回藤野さんはその林芙美子を見事にメタバースの世界で甦らせた。
話は変わるが、メタバースでの婚活デートが行われているらしい。
マッチングアプリでの出会いは、件数は増えるかもしれないが、不発に終わることもその分多い。
その点、企画者に言わせると、内面志向の出会いを求める人にとっては、外見が分からない中、様々な会話を十分にしてもらい、フィーリングや趣味の話が合い、そこから出会うことにより、外見が若干劣っていてもそんなに気にならないそうである。
主人公のサンタロウは定年後持て余して居るところにメタバースの世界に入り込む。
初めて出会ったのが、「本郷館」に住む「はやしふみこ」という女性?だった。
彼女は林芙美子の事が好きなのか、ハンドルネームを「はやしふみこ」と名乗る。
彼女がどのくらい林芙美子に精通しているのか興味が湧き、知らない体で接近する。
はやしふみこを介して「林芙美子」という作家がどの様な半生を送って来たのかを、文章を引用して読者に知らしめている。
ちょっとお節介な感じもしないでもないが、主人公のサンタロウ目線からメタバースの若き日のはやしふみこを見て、彼女の波瀾万丈の人生を上手く浮き上がらせている。
いただけないのは、サンタロウの設定年齢である。
メタバースに不慣れな感を出すために65〜70歳に設定されているが、考え方や話し方は、十代から二十代と思える。
その辺のギャップを最後まで埋められなかった。
サンタロウの設定を思い切って10代にして、年上の「はやしふみこ」に淡い恋心を持たせるという展開の方が面白くなったと思う。
そこに中国人の「ショウ」が恋敵のような絡み方をしても良いと感じた。
林芙美子という極貧生活を送っていた女性が、体を売ることなく爪に火を灯しながら日々一生懸命に生き、その世界から這い出そうと悪戦苦闘した姿が目に映った。
メタバースという次世代のツールを用い、林芙美子の半生を描いた試みは、作品を書く上で参考になると感じた。
数年前に藤野さん企画の林芙美子の足跡を辿る文学散歩に参加させてもらった事がある。同じ時期に放浪記を読んだ。
今回藤野さんはその林芙美子を見事にメタバースの世界で甦らせた。
話は変わるが、メタバースでの婚活デートが行われているらしい。
マッチングアプリでの出会いは、件数は増えるかもしれないが、不発に終わることもその分多い。
その点、企画者に言わせると、内面志向の出会いを求める人にとっては、外見が分からない中、様々な会話を十分にしてもらい、フィーリングや趣味の話が合い、そこから出会うことにより、外見が若干劣っていてもそんなに気にならないそうである。
主人公のサンタロウは定年後持て余して居るところにメタバースの世界に入り込む。
初めて出会ったのが、「本郷館」に住む「はやしふみこ」という女性?だった。
彼女は林芙美子の事が好きなのか、ハンドルネームを「はやしふみこ」と名乗る。
彼女がどのくらい林芙美子に精通しているのか興味が湧き、知らない体で接近する。
はやしふみこを介して「林芙美子」という作家がどの様な半生を送って来たのかを、文章を引用して読者に知らしめている。
ちょっとお節介な感じもしないでもないが、主人公のサンタロウ目線からメタバースの若き日のはやしふみこを見て、彼女の波瀾万丈の人生を上手く浮き上がらせている。
いただけないのは、サンタロウの設定年齢である。
メタバースに不慣れな感を出すために65〜70歳に設定されているが、考え方や話し方は、十代から二十代と思える。
その辺のギャップを最後まで埋められなかった。
サンタロウの設定を思い切って10代にして、年上の「はやしふみこ」に淡い恋心を持たせるという展開の方が面白くなったと思う。
そこに中国人の「ショウ」が恋敵のような絡み方をしても良いと感じた。
林芙美子という極貧生活を送っていた女性が、体を売ることなく爪に火を灯しながら日々一生懸命に生き、その世界から這い出そうと悪戦苦闘した姿が目に映った。
メタバースという次世代のツールを用い、林芙美子の半生を描いた試みは、作品を書く上で参考になると感じた。
克
克己 黎さん (91bqly4e)2024/2/17 19:01削除『本郷館』を読んで 克己 黎
林芙美子の生涯を、若い人やまったく知らない人にも、メタバースという世界に登場させることで、分かりやすく紹介している作品。
『放浪記』の作家としてしか、知らなかったため、私生児だったことや男性遍歴があったこと、従軍記者時期のことなど、知ることができたのはありがたかった。
また、本作を読んだ後に、Wikipediaを調べたら『めし』『浮雲』の作者とあった。
『浮雲』は高峰秀子と森雅之、岡田茉莉子の出演による成瀬巳喜男監督作品で、私も前に二度ほど観て、最高傑作だと感じたモノクロ映画である。ああ、あの『浮雲』を書いた作家の女性なのかと、『浮雲』のか弱い流されてゆく女性の悲哀を同性の作家が書いたのかと改めて驚いた。
作中の記述に次のような箇所があった。
[敗戦後多くの日本人や新聞社、学校の先生まで、ころりと「戦争反対」に変わったという。しかし芙美子は従軍作品があるため戦争協力者と看做されることになる。総力戦だった太平洋戦争で、文学は何を期待され、何をしてしまったのかは、戦後厳しく検証されたのだ。けれど自分がもしも戦争中に生きていたら街中で「反戦を訴える」なんてことはやはりできないと思う。その他多くの日本人と同様に戦争協力者になっていただろう。「飢えの恐怖」が染みついている芙美子には仕事を失う選択はできなかったと思う]※二十七頁、七行目から十五行目
まさにその通りで、作家や画家は陸海軍の従軍記者となり、その様子を、プロパガンダとして戦争を聖戦と誇張して市民に伝えたため、戦後、戦争責任を問われた。
しかし、国民総動員での戦争で家族が兵隊になり、敵地に行き、また女性は工場で働き、夫がいない家を守った時に、果たして反戦を唱えられるものがどれだけいたのか。
丸木位里・丸木俊夫妻の反戦絵画や、香月泰男のシベリア抑留時代から生まれた反戦絵画などは、戦後よく取り上げられるようになった。しかし、富士山の絵などの横山大観や、女性の絵で有名な宮本三郎、『みだれ髪』の表紙絵で知られる画家、藤島武二らも戦争に協力をしている。戦争に協力しなければ非国民だった時代のことである。
林芙美子も国民総動員での戦争だから、と作家として、仕事として、国民として、従軍したまでであって、戦後の批判は、不条理なものだと思った。
Wikipediaによると、葬儀委員長が川端康成であり、生前の芙美子の行動に対して、赦してあげてほしいとコメントしたとあり、奔放な男性遍歴と従軍作家活動、共産党との関連などに関してだと思われる。
林芙美子は四十七歳という若さで亡くなったが、作品は、今も読まれ、舞台化、映像化され、視聴されている。
『本郷館』の「はやしふみこ」や「ショウ」「サンタロー」を通して、今回あらゆる角度から林芙美子の生涯を読み解くことができた。「サンタロー」は藤野さんのメタバースであるだろう。
実に面白く、あっという間に読むことができ、藤野燦太郎氏の「読ませる」筆力が見事な出来栄えの作品であった。
2024.2.17克己黎
林芙美子の生涯を、若い人やまったく知らない人にも、メタバースという世界に登場させることで、分かりやすく紹介している作品。
『放浪記』の作家としてしか、知らなかったため、私生児だったことや男性遍歴があったこと、従軍記者時期のことなど、知ることができたのはありがたかった。
また、本作を読んだ後に、Wikipediaを調べたら『めし』『浮雲』の作者とあった。
『浮雲』は高峰秀子と森雅之、岡田茉莉子の出演による成瀬巳喜男監督作品で、私も前に二度ほど観て、最高傑作だと感じたモノクロ映画である。ああ、あの『浮雲』を書いた作家の女性なのかと、『浮雲』のか弱い流されてゆく女性の悲哀を同性の作家が書いたのかと改めて驚いた。
作中の記述に次のような箇所があった。
[敗戦後多くの日本人や新聞社、学校の先生まで、ころりと「戦争反対」に変わったという。しかし芙美子は従軍作品があるため戦争協力者と看做されることになる。総力戦だった太平洋戦争で、文学は何を期待され、何をしてしまったのかは、戦後厳しく検証されたのだ。けれど自分がもしも戦争中に生きていたら街中で「反戦を訴える」なんてことはやはりできないと思う。その他多くの日本人と同様に戦争協力者になっていただろう。「飢えの恐怖」が染みついている芙美子には仕事を失う選択はできなかったと思う]※二十七頁、七行目から十五行目
まさにその通りで、作家や画家は陸海軍の従軍記者となり、その様子を、プロパガンダとして戦争を聖戦と誇張して市民に伝えたため、戦後、戦争責任を問われた。
しかし、国民総動員での戦争で家族が兵隊になり、敵地に行き、また女性は工場で働き、夫がいない家を守った時に、果たして反戦を唱えられるものがどれだけいたのか。
丸木位里・丸木俊夫妻の反戦絵画や、香月泰男のシベリア抑留時代から生まれた反戦絵画などは、戦後よく取り上げられるようになった。しかし、富士山の絵などの横山大観や、女性の絵で有名な宮本三郎、『みだれ髪』の表紙絵で知られる画家、藤島武二らも戦争に協力をしている。戦争に協力しなければ非国民だった時代のことである。
林芙美子も国民総動員での戦争だから、と作家として、仕事として、国民として、従軍したまでであって、戦後の批判は、不条理なものだと思った。
Wikipediaによると、葬儀委員長が川端康成であり、生前の芙美子の行動に対して、赦してあげてほしいとコメントしたとあり、奔放な男性遍歴と従軍作家活動、共産党との関連などに関してだと思われる。
林芙美子は四十七歳という若さで亡くなったが、作品は、今も読まれ、舞台化、映像化され、視聴されている。
『本郷館』の「はやしふみこ」や「ショウ」「サンタロー」を通して、今回あらゆる角度から林芙美子の生涯を読み解くことができた。「サンタロー」は藤野さんのメタバースであるだろう。
実に面白く、あっという間に読むことができ、藤野燦太郎氏の「読ませる」筆力が見事な出来栄えの作品であった。
2024.2.17克己黎
里
里井雪さん (90k4n5mn)2024/3/6 20:38削除フルダイブ型のバーチャルリアリティと林芙美子、あえてのミスマッチを狙っておられるのでしょう。確かにこの組み合わせなら、ChatGPTでも思いつかないですね。とても面白く拝読いたしました。
ですが……。近未来SFがメインなのか? 林芙美子論なのか? 二兎を追うものになっている気がします。
SFをメインに据えるのであれば、「臭いや触覚が分かること」についての、仮想科学的な解説があるなど、もっとサイエンスしてほしいと思いました。
逆に、林芙美子論なら、すいません、ご無礼お許しください。私なら……、という話です。『転生したら林芙美子だった』はいかがでしょう? タイムスリップし、林芙美子になってしまった主人公の目的は「戦争協力者」というバッドエンドを回避すること。これだと、林芙美子の「生涯」をガッチリ描けると思います。
要は、どちらかに力点を置いて、主従関係が明確になるようなストーリーがよいのでは? と感じました。
ですが……。近未来SFがメインなのか? 林芙美子論なのか? 二兎を追うものになっている気がします。
SFをメインに据えるのであれば、「臭いや触覚が分かること」についての、仮想科学的な解説があるなど、もっとサイエンスしてほしいと思いました。
逆に、林芙美子論なら、すいません、ご無礼お許しください。私なら……、という話です。『転生したら林芙美子だった』はいかがでしょう? タイムスリップし、林芙美子になってしまった主人公の目的は「戦争協力者」というバッドエンドを回避すること。これだと、林芙美子の「生涯」をガッチリ描けると思います。
要は、どちらかに力点を置いて、主従関係が明確になるようなストーリーがよいのでは? と感じました。
い
いまほり ゆうささん (922q9o5y)2024/3/7 16:21削除「本郷館」を読んで
メタバースの世界に入り込み”はやしふみこ‘’に出会うことで、林芙美子の生きた時代や環境を体感していくというストーリーにワクワクしながら引き込まれて読みました。藤野さんが企画して下さった文学散歩もそうですが、作家の生まれた土壌を知ることでより作品を立体的に捉えられることを改めて感じました。ただ、この作品に使われている言葉の中で「両声類」「バ美肉」「ファントムセンス」などは私には意味がよくわからなかったです。
メタバースの世界に入り込み”はやしふみこ‘’に出会うことで、林芙美子の生きた時代や環境を体感していくというストーリーにワクワクしながら引き込まれて読みました。藤野さんが企画して下さった文学散歩もそうですが、作家の生まれた土壌を知ることでより作品を立体的に捉えられることを改めて感じました。ただ、この作品に使われている言葉の中で「両声類」「バ美肉」「ファントムセンス」などは私には意味がよくわからなかったです。
原
原りんりさん (923tbrlg)2024/3/8 10:34削除本郷館
メタバースでバーチャルな世界を体験する対象が、明治時代の古い建物だという発想が面白かったです。もともと他人の家を覗き込むようなスリルもあり、そこでまさかの林芙美子の日常に遭遇するのも興味深い作品へのアプローチの仕方だと思いました。林芙美子の好みの男性が、そろいもそろってダメンズだということにおおいに共感!! ただ彼女の貧困のレベルは、例えば「女工哀史」の重労働や口減らしで商家売られて売られていった女性達とは違うこともおさえておく必要があると思いました。少なくとも彼女は女学校出のインテリ女性で、当時の全般的な貧困を代表してはいないと思います。
本郷館は実際に80年代に研究会で幾度か使用したことがあり、あの重厚な建物は懐かしかったです。当時は修学旅行生の宿泊に使われていたようでした。
メタバースでバーチャルな世界を体験する対象が、明治時代の古い建物だという発想が面白かったです。もともと他人の家を覗き込むようなスリルもあり、そこでまさかの林芙美子の日常に遭遇するのも興味深い作品へのアプローチの仕方だと思いました。林芙美子の好みの男性が、そろいもそろってダメンズだということにおおいに共感!! ただ彼女の貧困のレベルは、例えば「女工哀史」の重労働や口減らしで商家売られて売られていった女性達とは違うこともおさえておく必要があると思いました。少なくとも彼女は女学校出のインテリ女性で、当時の全般的な貧困を代表してはいないと思います。
本郷館は実際に80年代に研究会で幾度か使用したことがあり、あの重厚な建物は懐かしかったです。当時は修学旅行生の宿泊に使われていたようでした。
野
野守水矢さん (91n68ykn)2024/3/8 14:24削除の作品の感想を書くにあたって、林芙美子の著作「新版 放浪記」(林芙美子, kindle版)と「戦線」(林芙美子,中公文庫, 中公eブックス, kindle版)を先に読んだ。後者には従軍作家としての漢口戦記「戦線」と満州の紀行「凍れる大地」が所収されている。
その上で本作品を読めば、これは林芙美子の文学についてのわかりやすい評論、解説である。「文学横浜の会」で「放浪記」と「戦線」について読書会をすれば、かくもあろうか、と思わせされた。
林芙美子は「放浪記」に文学で身を立てることに執念を燃やしながらそれもかなわず、極貧と絶望の生活を描いている。プロレタリア文学とされるが思想的な主義主張は一切なく、プロパガンダは見られない。ただ、ひたすらもがき苦しむ日常を日記として記録した体になっている
「戦線」は陸軍派遣の従軍作家の目で漢口攻略戦を描いたものである。銃後の戦意を高揚するミッションのため、破竹の勢いで進軍する日本軍を誇り、兵隊の苦労をねぎらっている。漢口陥落を喜ぶ姿は、その筆致から林芙美子の本心であると推測される。作品では「当時の政府の検閲もあって、こんな感じで記録してあるのです(p26)」と検閲に責を負わせているが、それだけだろうか、芙美子の本心でもあったのではないだろうか。その一方で、忖度したのか指示・暗示されて書いたのか文脈からは不自然な祖国賛美も、筆が迷っている感じのする箇所も見られる。
ショウの日本軍への怒りの感情が、「中国の人たちは怒っています」と報道や評論で見かける表現と同じ感じで、心の底からの怒りの感情が読み取れなかったのは残念である。
なお、作品では触れられていないが「凍てつく大地」に登場する満州人、支那人は人格についての描写がなく、単に風景の一部のような感じである。満州人、支那人は林芙美子の眼中に全くなかったことが見て取れる。
興味深いのは、「放浪記」に描かれた貧困に絶望する姿から時代の寵児となってからの「戦線」に見られる得意の絶頂を謳歌する姿の変貌である。
作品では、得意になって舞い上がった、飢えの恐怖で仕事を失いたくなかった等の推測が記されていて、私も読書会があれば同様の発言をしたと思うが、欲を言えばこういった論を支える資料が欲しいものである。一人の人間が、軽蔑されていた極貧生活から喝采を受ける立場になると、どのように変貌するのかには、大いに興味がある。
林芙美子について、メタバース上で水先案内人「はやしふみこ」と同行者「ショウ」とともに林芙美子存命当時の現場を訪ねて対話する、という構成はよく考えられている。現存しない現場をリアルに探訪するためにメタバースは好都合な設定であると、認識した。
私にとっては、読んだことのなかった林芙美子を知り、読むよい機会となりました。ありがとうございます。
その上で本作品を読めば、これは林芙美子の文学についてのわかりやすい評論、解説である。「文学横浜の会」で「放浪記」と「戦線」について読書会をすれば、かくもあろうか、と思わせされた。
林芙美子は「放浪記」に文学で身を立てることに執念を燃やしながらそれもかなわず、極貧と絶望の生活を描いている。プロレタリア文学とされるが思想的な主義主張は一切なく、プロパガンダは見られない。ただ、ひたすらもがき苦しむ日常を日記として記録した体になっている
「戦線」は陸軍派遣の従軍作家の目で漢口攻略戦を描いたものである。銃後の戦意を高揚するミッションのため、破竹の勢いで進軍する日本軍を誇り、兵隊の苦労をねぎらっている。漢口陥落を喜ぶ姿は、その筆致から林芙美子の本心であると推測される。作品では「当時の政府の検閲もあって、こんな感じで記録してあるのです(p26)」と検閲に責を負わせているが、それだけだろうか、芙美子の本心でもあったのではないだろうか。その一方で、忖度したのか指示・暗示されて書いたのか文脈からは不自然な祖国賛美も、筆が迷っている感じのする箇所も見られる。
ショウの日本軍への怒りの感情が、「中国の人たちは怒っています」と報道や評論で見かける表現と同じ感じで、心の底からの怒りの感情が読み取れなかったのは残念である。
なお、作品では触れられていないが「凍てつく大地」に登場する満州人、支那人は人格についての描写がなく、単に風景の一部のような感じである。満州人、支那人は林芙美子の眼中に全くなかったことが見て取れる。
興味深いのは、「放浪記」に描かれた貧困に絶望する姿から時代の寵児となってからの「戦線」に見られる得意の絶頂を謳歌する姿の変貌である。
作品では、得意になって舞い上がった、飢えの恐怖で仕事を失いたくなかった等の推測が記されていて、私も読書会があれば同様の発言をしたと思うが、欲を言えばこういった論を支える資料が欲しいものである。一人の人間が、軽蔑されていた極貧生活から喝采を受ける立場になると、どのように変貌するのかには、大いに興味がある。
林芙美子について、メタバース上で水先案内人「はやしふみこ」と同行者「ショウ」とともに林芙美子存命当時の現場を訪ねて対話する、という構成はよく考えられている。現存しない現場をリアルに探訪するためにメタバースは好都合な設定であると、認識した。
私にとっては、読んだことのなかった林芙美子を知り、読むよい機会となりました。ありがとうございます。
野
野守水矢さん (91n68ykn)2024/3/8 15:33削除追記:上記感想では、原典に基づいて「支那人」の呼称を用いました。
上
上終結城さん (90mdbym0)2024/3/12 20:13削除小説の創作は、ある意味、別人格の自分を創り出す作業でしょう。本作中でアバターとなった「僕」は、二重に置き換わった作者自身とも考えられます(作者自身 ⇒ 作中の僕 ⇒ メタバース世界のアバター(レッサーパンダ))。本作はアバターとなった「僕」が、かつて林芙美子が泊まった本郷館や木賃宿で宿泊することで、林芙美子の当時の生活や思考を追体験する、という実験的な作品です。作者のチャレンジ精神に敬意を表します。
作者は、歴史ある(いまは取り壊された)本郷館という大きな下宿屋に、無名だった頃の林芙美子や蒋介石が住んでいたことを知り、この小説を着想したのかもしれません。
数年前、横須賀の「記念艦 三笠」に入り、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着してVRで再現した日本海海戦の現場(三笠の艦橋)に立つ体験をしたことがあります。この臨場感は文字情報では味わえません。ただし、これは誰かによってプログラムされ提供された体験であり、100%受身の体験です。
もし小説のなかの描写(たとえば本作の本郷館内部)が読者の想像力を刺激して、音と映像とは異なる、もう一つの疑似体験をもたらすことができたら、それこそが言葉による小説の存在意義でしょう。本作を読んで、そんなことを考えました。
作者は、歴史ある(いまは取り壊された)本郷館という大きな下宿屋に、無名だった頃の林芙美子や蒋介石が住んでいたことを知り、この小説を着想したのかもしれません。
数年前、横須賀の「記念艦 三笠」に入り、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着してVRで再現した日本海海戦の現場(三笠の艦橋)に立つ体験をしたことがあります。この臨場感は文字情報では味わえません。ただし、これは誰かによってプログラムされ提供された体験であり、100%受身の体験です。
もし小説のなかの描写(たとえば本作の本郷館内部)が読者の想像力を刺激して、音と映像とは異なる、もう一つの疑似体験をもたらすことができたら、それこそが言葉による小説の存在意義でしょう。本作を読んで、そんなことを考えました。
れ
大倉 れんさん (91n21k7s)2024/3/14 12:05削除小説を読むということ自体が深い疑似体験。その小説の中にリアル生活があり、仮想疑似空間がある。時代を遡り、実小説を引用し、林芙美子の生きざまをたどりアバターと化した者同士が本音で議論する。何重もの入れ子のようなプロットでこういうのははじめて読んだ。斬新だと思った。読むのには頭の体幹というか想像の持久力が必要だった。
「放浪記」は読んだことも舞台を観たこともないが、興味深く面白く読んだ。
コンプライアンスと体裁が優先される現代社会では、自分の内面をさらけ出すことができるバーチャルな世界に身を投じることは、癒しを得て、自己肯定を回復させる有効な手段なのかもしれない。
「放浪記」は読んだことも舞台を観たこともないが、興味深く面白く読んだ。
コンプライアンスと体裁が優先される現代社会では、自分の内面をさらけ出すことができるバーチャルな世界に身を投じることは、癒しを得て、自己肯定を回復させる有効な手段なのかもしれない。
金
金田さん (92e9fkev)2024/3/15 18:03削除不思議な小説。
メタバースとかの新しい表現手段を用いた創作。
この小説では仮想空間を用いた林芙美子論であり、私生児と言う偏見に対する問題提起のようにも思う。
林芙美子の戦争責任にも触れ中国戦線についても触れているが、現代の戦争にも触れて戦争そのものを批判する、のもありかなとも思った。
メタバースとかの新しい表現手段を用いた創作。
この小説では仮想空間を用いた林芙美子論であり、私生児と言う偏見に対する問題提起のようにも思う。
林芙美子の戦争責任にも触れ中国戦線についても触れているが、現代の戦争にも触れて戦争そのものを批判する、のもありかなとも思った。
池
池内健さん (92jz72t6)2024/3/19 20:11削除面白い小説を読むと舞台となった場所を訪ねたくなる。この作品では、現実には解体されてしまった本郷館をヴァーチャル世界で訪問する。仮想空間だからすでに亡くなっている作家(の身代わり)に質問をぶつけることも可能で、作家の世界観をより深く理解できる仕組みになっている。作中には<あらすじを追>うだけだった読書が<「体験読み」とでもいうべきものに変わっていくようにも思う>という記述もある。より深く小説世界を理解している人の解釈を聞くことで自分の理解も深まるということでいえば、読書会もヴァーチャル世界訪問に近い効能があることにも気づかせてくれた。
作中には「あなたはあんパンを街角で売って暮らせますか。恥ずかしくないですか。親戚がなんというか。学校でなにかいわれないかとか、私ならそう考えますよ」というセリフが出てくる。中流以上の家庭においては(女性、特に若い女性が)働かなければ生活できないという状況自体が恥ずべきものであった時代だったということだろう。「日本の大正、昭和の初めにあたる時代の中国には、物売り、物乞いなんてごまんといたようだよ」と、「物売り」と「物乞い」を同列に扱うセリフもある。今は夫婦共働きが当たり前だし、目端の利いた高校生や大学生が起業するのも珍しくないので、隔世の感があった。
作中には「あなたはあんパンを街角で売って暮らせますか。恥ずかしくないですか。親戚がなんというか。学校でなにかいわれないかとか、私ならそう考えますよ」というセリフが出てくる。中流以上の家庭においては(女性、特に若い女性が)働かなければ生活できないという状況自体が恥ずべきものであった時代だったということだろう。「日本の大正、昭和の初めにあたる時代の中国には、物売り、物乞いなんてごまんといたようだよ」と、「物売り」と「物乞い」を同列に扱うセリフもある。今は夫婦共働きが当たり前だし、目端の利いた高校生や大学生が起業するのも珍しくないので、隔世の感があった。
港
港朔さん (92fwbt2d)2024/3/26 11:20削除林芙美子の『浮雲』は読んだけれど『放浪記』は、読んでいない。読みたいとはずっと思っていてまだ読んでいない。改めて読みたいと思いました。小説家というのは、たいてい良家に生まれ育った人であるが、ごくたまに下層階級出身の人もいる。その一人が林芙美子であって、そんな意味でも読みたい作家の一人でした。メタバースによる林芙美子体験という構成の、この物語はとても面白かったです。
山
山口愛理さん (92ty90w3)2024/4/1 15:32削除昨年の秋、広島の尾道に行った時に急に雷雨になり、意図せず駆け込んだのが「尾道林芙美子記念館」だった。芙美子が思春期を過ごした尾道での旧宅がそのまま記念館になっていた。写真や原稿、資料、着物や愛用品なども置いてある。林芙美子についてそれほど詳しくなかったのだが、偶然訪れることができて旅の良い記念になった。
『本郷館』を読んで、そのことを思い出した。だが本作はメタバースの世界で、はやしふみこと名乗る少女と出会う話。中国人ショウと主人公サンタローのアバターたち三人は、その時代の街並みの古い家屋で林芙美子についての文学談義に熱中する。
この発想は面白かった。昔の街を闊歩するだけでなく、他の住民たちと討論までしてしまうのだから。藤野さんの書く物はジャンルが広いのだが、今回は予想外な世界だった。メタバースで「古い小説を追体験」できたら確かに面白いだろう。いずれはメタの世界で五感全てを駆使できるようになるかもしれない。
ただ、林芙美子に関する記述や戦争に関する討論の部分はかなり固くリアル。この固さとアニメ風なアバターが集うメタバースの不思議な世界のギャップを、どう感じるかというところが論点だと思う。
『本郷館』を読んで、そのことを思い出した。だが本作はメタバースの世界で、はやしふみこと名乗る少女と出会う話。中国人ショウと主人公サンタローのアバターたち三人は、その時代の街並みの古い家屋で林芙美子についての文学談義に熱中する。
この発想は面白かった。昔の街を闊歩するだけでなく、他の住民たちと討論までしてしまうのだから。藤野さんの書く物はジャンルが広いのだが、今回は予想外な世界だった。メタバースで「古い小説を追体験」できたら確かに面白いだろう。いずれはメタの世界で五感全てを駆使できるようになるかもしれない。
ただ、林芙美子に関する記述や戦争に関する討論の部分はかなり固くリアル。この固さとアニメ風なアバターが集うメタバースの不思議な世界のギャップを、どう感じるかというところが論点だと思う。
十
十河さん (934opo11)2024/4/3 05:57削除・メタ世界に入りこむという、チャレンジに挑んだ小説。
・どうして本郷館なのか、どうして林芙美子、プロレタリア文学、娼婦、私生児なのか?…… 主題が限定的なものになった感がある。メタ世界創出との必然性がよく分からなかった。
・しかし、新しいものへの挑戦は、それだけでも評価されるべきだと思った。
・どうして本郷館なのか、どうして林芙美子、プロレタリア文学、娼婦、私生児なのか?…… 主題が限定的なものになった感がある。メタ世界創出との必然性がよく分からなかった。
・しかし、新しいものへの挑戦は、それだけでも評価されるべきだと思った。
返信
返信15
Copyright © 文学横浜第55号掲示板, All Rights Reserved.
Powered By まめわざ(アクセス解析/広告のプライバシーポリシー・無料ホームページを作る)